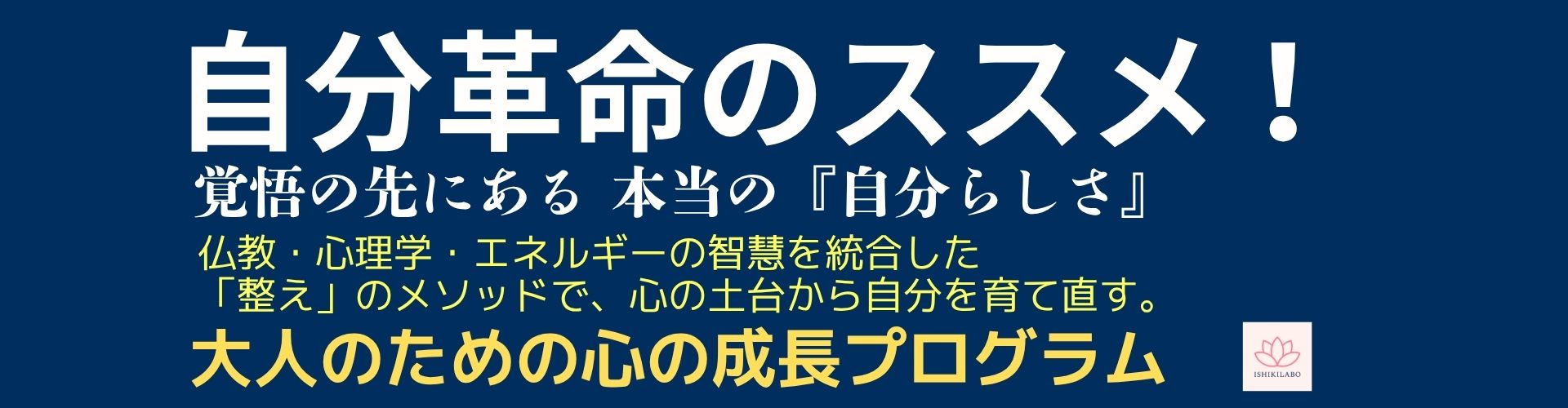こんにちは。
エネルギー調整セラピストとして活動している
かんまにです。
※最初にちょっとだけお伝えしておきます。
今回の記事を書き終えたとき、
自分でも
「これ…コラムじゃなくて有料セミナーじゃない?」
と思いました。(^^;
かなりの長文に仕上がっていますので、目印となる目次も入れておきました。
コーヒーでも飲みながら、気になる章からゆっくり読んでみてください。
かなりのボリュームですので何日かに分けて読むのもアリです。
きっとこの記事を読み終えたとき、あなたの中の“何か”が変わっているはずです。
「じゃあ、セミナーに参加してみよう!」と決めて、自分の意志で時間を作ることで、内容が自分の中にスッと染み込んでいきます。
あなたは今、過去の出来事や未来への不安に、心を揺らされていませんか?
ふとした瞬間に
「あの時、こうしていれば…」と過去を悔やみ、
まだ訪れていない未来に
「もし、こうなったらどうしよう」と怯える──。
わたし達は、本来「今」にしか生きられないはずなのに、
意識は簡単に時間を越えて過去や未来をさまよいます。
そして、そのさまよいが長引くほど、心のエネルギーは削られていきます。
このコラムでは、「過去を癒し、未来を創るための心の整え方」を、
仏教・心理学・スピリチュアル・最新科学の視点からお伝えします。
今回の記事を読むことで
- 過去に植え付けられた価値観やトラウマを手放すヒントが得られる
- 性やお金といった強いエネルギーを健全に扱う視点が身につく
- 自分の軸を保ちながら、他者の意思も尊重できる未来ビジョンが描ける
もし、このまま何も変えずに過ごすなら──
あなたは無意識のうちに、過去の価値観に縛られたまま、同じ悩みや葛藤を繰り返すでしょう。
性やお金といったテーマを避け続けることで、本来のエネルギーは滞り、
やがて自己否定や孤立感、信頼できる人間関係の喪失につながるかもしれません。
これは、「何の変化もない現状維持ルート」ともいえます。けれど、今この瞬間から「過去を癒し、未来を創る」という選択をしたなら──
過去の痛みさえも成長の糧に変え、性もお金も人生を豊かにするための力として扱えるようになります。
そして、自分と他者の意思を尊重し合える“セラピスト的な生き方”が、
あなたの未来の当たり前になります。
これは、「未来創造ルート」と呼べる道です。
過去と未来は「今」でつながっている
過去は変えられないが、意味は変えられる
私たちが経験してきた過去は、事実として変えることはできません。
たとえどんなに悔やんでも、その出来事そのものをなかったことにはできないのです。
しかし、その過去に「どんな意味を与えるか」は、今の自分が選び直せます。
これは心理学でいうリフレーミングです。
※リフレーミングとは、物事の見方や意味づけの枠(フレーム)を変えることで、同じ出来事でも新しい価値や可能性を見出す方法です。
たとえば──
子どもの頃、
「あんたなんか、ウチの子じゃない!」
「お前のような出来の悪い生徒は見たことが無い!」
そんな親や教師からの一言で深く傷ついた経験があるとします。
その記憶を「わたしが愛されなかった証拠」と解釈して、その記憶をずっと手放せずに持ち続けていれば、それが自己否定の種となり、大人になってもその自己否定の芽が育っていき、成長し続けます。
しかし、その出来事を「その一言があったからこそ、人の痛みに敏感になれた」と再解釈すれば、
同じ記憶が、自分の強みや使命感の源に変わり、先ほどの自己否定の芽から、今度は美しい花が咲き誇ります。
これは決して「無理やりポジティブになる」という話ではありません。
仏教の因果観では、すべての出来事は原因(因)と条件(縁)が重なって生じる(果)とされます。
その出来事があなたに何をもたらしたのか?(報)を、今の視点から再評価する──
それこそが過去を癒す第一歩なのです。
ここで一つ、あなたの記憶に残っている大きな出来事に対して、あなた自身に問いかけてみてください。
「あの出来事がなかったら、私は今どんな自分だっただろう?」
その問いは、過去の中に埋もれた“成長の種”を見つけるきっかけになります。
未来はまだ白紙──心の状態が軌道を決める
未来は、まだ何も描かれていない真っさらなキャンバスのようなものです。
けれど、そのキャンバスにどんな絵を描くかは、今この瞬間の心の状態が大きく左右します。
そして、わたし達の思考や感情は、無意識のうちに日々の選択を決めていて、その小さな選択の積み重ねが、数か月後、数年後の未来を形づくっていきます。
同じ出来事でも軌道が変わる
たとえば、職場で上司にきつい言葉をかけられたとします。
その瞬間、心が「やっぱり自分はダメなんだ」と沈み込むと、自己評価は下がり、
チャレンジの機会から距離を取るようになります。
その結果、未来の可能性は縮んでいくでしょう。
一方で、「あの人は忙しさやストレスで余裕がなかっただけ」と受け止められれば、
自分の価値を不必要に下げずに済みます。
この姿勢は新しい挑戦や人間関係を引き寄せ、未来の選択肢を広げます。
同じ出来事でも、心の状態が異なれば、未来の軌道は大きく変わるのです。
心理学と仏教の視点
心理学では、こうした現象を「選択の連鎖」と呼びます。
一度ネガティブな解釈をすると、それに沿った選択を繰り返し、同じ現実を再生産してしまうのです。
仏教でも、「一念三千(いちねんさんぜん)」という考え方があります。
これは、一瞬の心(念)が、未来の無数の現象に影響を及ぼすという教えです。
今の心の在り方が、これから訪れる出来事の質を決めていくという意味では、心理学と共通しています。
自分の心を「未来の舵」にする
未来を思い描くとき、私たちは外側の条件ばかりを気にしがちです。
しかし、本当に重要なのは「今の心の質」です。
怒りや不安に支配されたままでは、どんなに願っても未来は揺らぎやすくなります。
逆に、落ち着きや信頼感をベースにした心の状態は、選択や行動を安定させ、
未来を自分らしくデザインできる土台になります。
ここで一つ、あなたの想像力をフル活用して、あなた自身に問いかけてみてください。
「今の私は、未来をどんな世界に描こうとしているのだろう?」
その問いは、あなたの中に眠る“未来の設計者”を目覚めさせます。
このように、未来は外から与えられるものではなく、今の心の状態から自然に形づくられていくものです。
だからこそ、未来を変えたければ、まずは今の心を整えることが一番の近道なのです。
『ゆる』──他人に植え付けられた価値観をほどく
子ども時代に刷り込まれた「性」と「お金」のイメージ
わたし達は、幼い頃から家庭や学校、社会を通して「性」と「お金」に関する価値観を受け取ります。
その多くは、当時の大人たちが持っていた常識や文化背景を色濃く反映しています。
たとえば、
- 「そんなことは恥ずかしいから言っちゃダメ」
- 「お金の話をするのは下品」
といった言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるかもしれません。
こうした言葉は、子どもの心に「性=恥ずかしい」「お金=汚い」というラベルを貼り付けます。
そして、そのラベルは無意識のうちに大人になっても残り、日常の判断や行動に影響を与え続けます。
幼少期の刷り込みが消えにくい理由
心理学では、6〜12歳頃までに形成された価値観や思い込みは、潜在意識の奥深くに刻まれると言われます。
これは「スキーマ(認知の枠組み)」と呼ばれ、その後の情報処理や意思決定に強く影響します。
・脳の仕組みから見た「刷り込み」
子ども時代は脳の前頭前野がまだ発達途上で、情報を批判的に分析する機能が弱いため、
親や教師の言葉をそのまま事実として吸収しやすいのです。
つまり、幼少期に刷り込まれた価値観は、あたかも「それが世界の真実」であるかのように感じられ、
成長してからも自動的に反応してしまうのです。
「性」と「お金」の共通点
一見まったく異なるテーマに見える「性」と「お金」ですが、文化的には共通点があります。
- タブー視されやすい(公の場で語りづらい)
- 感情と結びつきやすい(恥・欲望・恐れ・罪悪感)
- 使い方次第で成長にも破滅にもなる
このため、正しい知識を学ぶ機会が少なく、結果として偏見や誤解が残りやすいのです。
無意識のラベルがもたらす影響
性やお金に「恥ずかしい」「汚い」という無意識のラベルが貼られていると、
- 健全なコミュニケーションを避ける
- 必要な学びを得ないまま行動する
- 欲求や必要を素直に表現できない
といった問題が起こります。
私の知人の例
ある女性は、親がお金で苦労をしたために、お金の話をするのは下品だと厳しく徹底的に教えられて育ちました。
その彼女が大人になり、ビジネスを始めようとしたのですが、商品の説明まではイキイキと話せるのに、いざ金額の話になった途端に声が小さくなり、自分の商品の価値を十分に伝えられません。
その結果、優れたスキルを持ちながらも、収入はなかなか伸びませんでした。
これはお金の話をすることが、仕事であっても下品だと思い込んでしまっていることが原因なのです。
性がタブー視されることで生まれる誤解と偏見
性の話題は、多くの文化や家庭で長い間「触れてはいけないもの」とされてきました。
その背景には、宗教的な戒律や道徳観、または「子どもを守るため」という善意もあります。
しかし、タブー視することは必ずしも守ることにはならず、むしろ危うさを生む場合があります。
性にまつわる正しい知識や健康的な価値観が得られないまま大人になると、
誤った情報や偏ったイメージが心の土台となってしまうのです。
その歪んだ心の土台が正されないので、性犯罪が後を絶たないのです。
情報不足がもたらす「歪んだ常識」
情報が不足していると、人は身近にある情報源から補おうとします。
しかしそれが、同年代の噂話や、刺激ばかりを強調するインターネットの断片的な知識だったとしたらどうなるでしょうか?
そこから得られるのは、健全な理解ではなく、断片的で歪んだ“常識”です。
性教育をほとんど受けずに育った若者が、恋人との関係で相手を思いやる行為を「格好悪い」と感じていたケースがあります。
彼の頭の中にあったのは、ネット動画から得た非現実的で一方的なイメージだけ。
「性=支配」「性=恥ずかしい」という極端な枠組みが、自然な愛情表現を妨げていました。
抑圧は必ずどこかで噴き出す
心理学では、強く抑圧した感情や欲求は、形を変えて噴き出すと言われます。
性をタブー視して否定し続ければ、そのエネルギーは健全な表現を失い、
依存・衝動・支配欲など、歪んだ形で表れる可能性があります。
仏教的視点
仏教では、煩悩を無理に押さえ込むのではなく、気づきと共に昇華させることが説かれています。
「煩悩即菩提」という言葉は、まさに抑圧ではなく理解と変容の大切さを示しています。
タブー視を解くことは、予防にもなる
性をオープンに話せる環境は、子どもや若者が正しい知識を得る場を作ります。
これは、性犯罪や望まない妊娠を防ぐだけでなく、自分や相手を尊重する意識を育てる予防策でもあります。
健全な知識は「やってはいけないこと」を教えるだけでなく、
「どうすればお互いが安心できる関係を築けるか」というポジティブな視点も与えてくれます。
このように、タブー視は一見安全に見えても、実は危うい「無知の温床」になり得ます。
だからこそ、性について正しく語り合える土台を作ることが、個人の幸せにも社会の安全にもつながります。
お金も同じ構造で歪む「価値観の連鎖」
お金のテーマも、性と同じく多くの家庭や文化でタブー視されやすいものです。
「いくら稼いでいるのか?」といった「お金の話は下品」、
「お金がたくさん稼げる方法を考える」といった「稼ぐことは欲深いこと」、
そんな価値観を無意識のうちに刷り込まれている人は少なくありません。
このタブー化は、性の場合と同じ構造を持っています。
正しい知識や健全な価値観が得られないまま成長することで、偏った行動や誤解が固定化されるのです。
お金にまつわる「沈黙の教育」
お金に関して、家庭で体系的に学んだ経験がある人はどれくらいいるでしょうか。
多くの人は、親が口にする断片的な言葉や、社会で見聞きした印象から価値観を作り上げます。
よくある刷り込みの例
- 「お金は汗水たらして苦労して稼ぐもの」
- 「お金の話をする人はいやらしい」
- 「貯金がないと不安」
これらは一見まっとうな教えにも思えますが、その裏側には
「お金=苦労」「お金=汚い」「お金=不足して当然」といった感情的な枠組みが隠れています。
タブー化が招く負のスパイラル
お金の話を避け続けると、次のような負の連鎖が生まれます。
- 知識不足──正しい運用法やリスク管理を学べない
- 誤解の固定化──お金への恐れや嫌悪が強まる
- 行動の制限──必要な投資や挑戦を避けてしまう
わたしがおこなった聞き込み調査による実例
17人中8割以上の人は「お金は使うとなくなる」という信念(自我)を子どもの頃から持っているようでした。
そのため、大切な学びや自己投資に必要なまとまったお金が使えず、ストレス発散の旅行や外食、また競馬やパチンコのようなギャンブルなどに散財してしまい、結果的に収入や人生の可能性を広げる機会を逃していました。
この使い方であれば確実にお金は使えばなくなります。
ですが、お金の増やし方を学ぶことに投資をすれば、学べば学ぶほどお金を生み出す力が付きますので「お金は使えば増える」という発想に進化していきます。
性とお金の共通構造
性とお金は、ともに
- タブー化されやすい
- 強い感情と結びつく
- 偏った情報のまま大人になると扱い方を誤る
という共通点があります。
そしてどちらも、正しい知識と健全な価値観を持つことで、
成長と豊かさを生み出すエネルギーへと変わります。
意識的に学び直す必要性
大人になってからでも、性やお金に関する価値観は書き換えられます。
ポイントは、「自分がどんな価値観を持っているのか」に気づくこと。
それが、自動操縦のように働く古いプログラムを停止させ、新しい選択肢を広げる第一歩です。
『浄』──性のエネルギーを肯定する視点
フロイトが性欲トラウマを重視した理由
精神分析の父、ジークムント・フロイトは、人間の行動や感情の多くが無意識によって支配されていると考えました。
その無意識の中でも、特に強力なエネルギーとして位置づけたのが「性欲」、つまりリビドーです。
フロイトは、性に関する感情や欲求が強く抑圧されると、それが心の奥で膨らみ、やがて神経症や不安、衝動的な行動として現れると主張しました。
なぜ性欲は特別なのか
フロイトによれば、性欲は単なる肉体的欲求ではありません。
それは人間が生き延び、種を保存するための根源的な力であり、同時に創造性や自己実現とも密接に関わっています。
性欲=生命エネルギーの一形態
性欲は、赤ちゃんが母親に抱かれて安心する感覚や、誰かを愛おしいと思う感情にも通じる「結びつきのエネルギー」です。
それを否定したり抑え込んだりすると、人は深い孤独や疎外感を抱きやすくなります。
抑圧がもたらす影響
性欲をタブー視して抑圧すると、そのエネルギーは健全な方向へ発散できなくなります。
すると、攻撃性や依存、過剰な支配欲といった形で表面化することがあります。
臨床例
性に対して強い罪悪感を抱えていた男性が、パートナーとの関係を避け続けた結果、
他者との感情的なつながり全般を避けるようになり、孤立感から慢性的なうつ状態に陥っていました。
フロイトの視点の限界と現代の解釈
フロイトの理論は100年以上前のものであり、現代では修正や発展が加えられています。
しかし、性に関する抑圧が心身に影響するという核心は、多くの臨床現場で今も確認されています。
特に、性に関するトラウマの解消は、自己肯定感や人間関係の改善に直結する重要なテーマです。
空海と『理趣経』──「煩悩即菩提」の教え
真言宗の開祖・空海(774〜835)は、日本仏教史の中でも特に大胆な教えを説いた僧侶の一人です。
その中でも象徴的なのが、『理趣経(りしゅきょう)』に説かれる「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」という思想です。
この言葉は、「煩悩=悟りの種であり、それを否定するのではなく活かしてこそ悟りに至る」という意味を持ちます。
性欲や執着といった、一般には“悪い(タブー)”とされる心の働きも、方向さえ変えれば人を成長へ導くエネルギーになる──これが空海の革新的な視点です。
『理趣経』の背景
『理趣経』は、密教の経典の中でも特に人間の欲望に正面から向き合った内容を持ちます。
そこでは、欲望を単純に否定するのではなく、「智慧によって昇華する」ことが説かれます。
欲望は火と同じ
火は、放置すれば人や家を焼き尽くす危険なものです。
しかし、適切に管理すれば暖を取り、料理を作り、生活を豊かにします。
欲望も同じで、無知のまま扱えば破壊的になり、智慧を持って扱えば創造的な力になります。
煩悩を昇華させるプロセス
空海の教えでは、煩悩を単に抑え込むのではなく、次のような段階で扱います。
- 気づく──自分の中の欲望や執着を否定せず観察する
- 理解する──その欲望が生まれた背景や動機を知る
- 方向づける──他者や社会の利益に役立つ形へ変換する
性欲の場合
「自分だけの満足」に向かっていたエネルギーを、「相手との信頼や愛情を深める行為」へと変える。
この変換こそが、煩悩を菩提へと変える道です。
現代に生きる『理趣経』の智慧
現代社会では、欲望を刺激する情報が溢れています。
その中で、ただ欲望を押し殺すのではなく、どう扱えば成長につながるかという視点を持つことはますます重要です。
空海の「煩悩即菩提」は、性やお金、地位や名誉といった強い欲求を敵視するのではなく、
それらを自己成長や他者貢献のために活かす道を示してくれます。
性とお金のエネルギーに共通する本質
性とお金は、一見するとまったく別の領域に思えます。
しかし、深く掘り下げると、どちらも「エネルギーの流れ」という共通点を持っています。
それは、扱い方によって人を豊かにも貧しくもする、中立的で強力な力です。
善悪のラベルは後から人間が貼ったものであり、本来はニュートラルな存在なのです。
どちらも「循環」が本質
心理学でも経済学でも、エネルギーは循環することで健全な状態を保ちます。
- 性のエネルギーは、愛情・信頼・生命力として人と人をつなぐ
- お金のエネルギーは、価値・モノ・サービスを循環させて人と人をつなぐ
水の流れのたとえ
性やお金は、水に似ています。
流れていれば清らかさと潤いを与えますが、滞ると淀み、濁っていきます。
流れをせき止めすぎても、あふれさせすぎてもバランスを崩します。
タブー視が滞りを生む
性もお金も、タブー視されることでその流れが滞ります。
- 性:恥や罪悪感による抑圧
- お金:恐れや不足感による制限
滞りはやがて、依存や搾取、孤立感や貧困といった形で現実に反映されます。
健全な流れを保つための3つのポイント
- 知識──正しい理解が偏見や恐れを減らす
- 尊重──相手の意思と境界を守る
- 目的意識──自分や他者の成長に役立てる方向へ使う
仏教的な補足
仏教では「布施」という教えがあります。
これは、お金や物だけでなく、時間・知恵・思いやりを与えることも含まれます。
性やお金のエネルギーも、この布施の精神で使うことで、自分も相手も満たされる循環が生まれます。
この視点を持つと、性もお金も「危険なもの」ではなく「成長と豊かさを生み出す資源」へと認識が変わります。
これが、次の章「新しい判断基準を創造する」につながります。
『覚』──新しい判断基準を創造する
善悪の二元論から離れ、エネルギーの質を観る
多くの人は、物事を「良い」か「悪い」かの二元論で捉えます。
これは人間の思考の自然な傾向ですが、この枠組みを「ジャッジ」と呼び、時にわたし達を縛り、柔軟な発想や選択を阻むことがあります。
性やお金についても同じです。
- 性=良い/悪い
- お金=きれい/汚い
といった極端なラベル付けは、エネルギーそのものの性質を見えなくさせます。
エネルギーに善悪はない
仏教や物理学の視点から見れば、性もお金も「ただ存在する力」です。
善悪は、その使い方と意図によって初めて生まれます。
ナイフのたとえ
ナイフは料理にも使えれば、人を傷つけることもできます。
道具そのものは中立であり、どう使うかは持つ人の意識と技量次第です。
性もお金も、このナイフと同じく、使い手の心が方向性を決めます。
二元論から離れると自由が広がる
「これは良い」「これは悪い」という単純な枠から離れることで、
わたし達はもっと多様な選択肢を見つけられるようになります。
心理学では、これを「認知の柔軟性」と呼び、ストレス耐性や創造性の高さに直結するとされます。
たとえば性のエネルギーも、お金のエネルギーも、
「これは危険」と決めつけて封じ込めるよりも、
「どう使えば役立つか?」と問う方が、健全な流れを生みやすくなります。
仏教的視点での「質の観察」
仏教では「色即是空(しきそくぜくう)」と説かれます。
これは、形あるものは固定的な本質を持たないという意味です。
性やお金も本質的に「空」であり、わたし達の意識や行動によって質が変わります。
質を見る問い
- このエネルギーは、今どんな方向に流れているか?
- それは自分や周囲を成長させているか?
- それとも停滞や破壊につながっているか?
この問いを持つことが、エネルギーをより良い方向へと舵取りする第一歩です。
わたし自身、この視点を持つことで、性やお金を無条件に恐れたり拒否したりする必要がなくなり、
自分の意志で使い方を選べる自由が広がりました。
性とお金を「成長の資源」として扱う方法
性とお金は、どちらも使い方によっては破壊的にも創造的にもなり得る強いエネルギーです。
そのため、意識的に「成長の資源」として扱う姿勢が重要です。
ここでは、そのための具体的な方法を4つのステップにまとめます。
① 正しい知識を学ぶ
性やお金についての誤解や偏見は、知識不足から生まれます。
最新の性教育や金融リテラシーを学ぶことで、不要な恐れや罪悪感が減り、健全な判断がしやすくなります。
仮想通貨の例
金融知識がないまま、儲かるからと言われて仮想通貨を始めた人が、当時流行った「億り人」になったまでは良いのですが、年度末に支払う税金の知識がまったく無く、トラブルで苦しんだケースがあります。
知識があれば回避できた問題も、無知であるがゆえ「危険の扉」を開いてしまうのです。
② 感情や欲求を否定せず観察する
欲求や感情を抑え込むのではなく、まずは「自分は何を求めているのか?」を素直に観察します。
これは心理学でいうマインドフルネス的な自己観察に近い方法です。
観察の問いかけ
- 今、私は何を欲している?
- その欲求は安心や喜びを生むものか?
- それとも不安や恐れから来ているか?
③ 他者の意思や境界を尊重する
性やお金を扱う上で避けられないのが、相手の意思と境界線です。
これを無視すると、信頼関係は一瞬で壊れます。
逆に、境界を尊重する姿勢は、長期的な信頼と豊かさをもたらします。
仏教の「不殺生」と「布施」
他者を傷つけないこと(不殺生)と、惜しまず分かち合うこと(布施)は、性やお金の扱いにもそのまま適用できます。
④ エネルギーを創造的な方向に使う
性のエネルギーは、芸術・スポーツ・学びなどの創造活動にも転換できます。
お金のエネルギーは、自己投資や社会貢献、誰かの夢を応援する資金に変えることができます。
性にまつわる罪悪感やトラウマを、創造や社会的行動に昇華させた日本の実例として、以下の作品が挙げられます。
- 伊藤詩織『Black Box』
性暴力被害の告白と司法の闇を描いた記録。あえて語ることで社会の無関心に問いを投げ、癒しと変化を促した記録です。- 香月真理子『欲望の行方:子どもを性の対象とする人たち』
自身の被害体験から、対話を通じて“理解と寛容”を模索したノンフィクション。性への偏見ではなく、対話の可能性に目を向けています。- 三島由紀夫『仮面の告白』
自伝的小説で、自身の性に関する苦悩を詩的に表現し、文学を通して“理解”という創造へ変換した日本文学の傑作です。
ここまでの4つのステップを意識すると、性やお金は「怖いもの」や「汚いもの」ではなく、
人生を育てるための栄養源として活かせるようになります。
セラピスト的生き方──自分と相手、双方の意思を尊重する
セラピスト的な生き方とは、相手の心に寄り添いながらも、自分の軸を失わない在り方です。
これは単に「優しくする」ことではなく、互いの意思と境界線を尊重する成熟した関係性を築くことを意味します。
自分も相手も大切にする関係
「自分を優先したら、相手を傷つけるのではないか?」
「相手を優先しすぎて、結局自分が疲れてしまった!」
そんな経験はありませんか?
セラピスト的な生き方は、このどちらにも偏らず、“わたし”と“あなた”の両方を尊重する姿勢を取ります。
イメージするなら、シーソーの真ん中にそっと立ち、左右の重さを確かめながらバランスを保っていくような感覚です。仏教ではこの考え方を『中道』といいます。
境界線(バウンダリー)の重要性
境界線(バウンダリー)と聞くと、壁のように感じるかもしれません。
でも本当は、お互いを守るための透明なフェンスのようなものです。
- 相手の感情は、相手のもの
- 自分の選択は、自分が決める
- 断ることは、拒絶ではなく自己尊重
想像して頂くと理解しやすいですが、どんなに大好きな人であっても、24時間ずっと一緒に居るわけにはいきません。境界線があるからこそ、安心して関われる距離感が生まれます。
「同意」は返事だけではない
性やお金のように影響力の大きいテーマでは、同意(コンセント)が必須です。
そして、それは単に「はい」と返事をもらうだけではありません。
相手が状況を理解し、選択に納得し、心から安心できる状態──
これが本当の意味での同意です。
日常の中の同意
たとえばデートの誘いなら、
「行こうよ」だけでなく、「どう思う?」と尋ねてみる。
その一言が、相手の安心感を生み、関係性を深めます。
自分の軸を保つことが相手を守る
「相手のため」と言いながら、自分を犠牲にしていないでしょうか。
軸を保つことは、わがままではなく、お互いの自由と安全を守るための条件です。
仏教には「自灯明・法灯明」という言葉があります。
これは「自らを灯とし、真理を灯とせよ」という教え。
他者に依存するのではなく、自分の内側にある光を道しるべにすることが、結局は相手をも安心させるのです。
この在り方は、セラピストやカウンセラー、ヒーラーやコーチだけでなく、誰にとっても人生を豊かにするスキルです。
「わたし」も「あなた」も尊重する関係性は、性やお金のエネルギーを健全に循環させる土台となります。
『動』──過去を癒し、未来を育てる実践
未来の自分からの手紙ワーク
なぜ未来の自分からなのか
多くの人は、希望のような「なりたい自分」として、未来に向かって手紙を書きます。
しかし、このワークでは未来の自分が「今の自分」に手紙を送る形をとります。
なぜなら、未来の自分は、すでに今の課題を乗り越えた存在だからです。
その視点からの言葉は、励ましや洞察に満ちていて、現実的なアドバイスになることが多いのです。
ワークのやり方
- 静かな場所を選ぶ
携帯や通知をオフにして、自分だけの時間を確保します。 - 未来の自分をイメージする
5年後、10年後など、あなたが望む未来にいる姿をできるだけ細かく描きます。
(服装、環境、人間関係、感情など) - 未来の自分として書く
「○○へ」と自分の名前を書き、未来の自分の立場で、今の自分に必要なメッセージを綴ります。 - 読み返す
書き終えたら、今の自分としてその手紙を読みます。
そこには意外なヒントや勇気づけが隠れているはずです。
ポイント
- 批判や命令ではなく、優しく包む言葉で書く
- 「こうなったよ」という完了形で未来を描く
- 実際のアドバイスや行動案も混ぜる
体験者の声
最初は疑いしかありませんでした。
でも、三日坊主のクセを直すために1ヶ月間、日記をつけようと決めました。
そして解説のようにリアルに想像しながら、未来の自分をねぎらうようにちょうど1か月後のページに
「もう大丈夫だよ。あの選択をよく決断できたね。あの勇気がすべてを変えたんだよ。」
というメッセージを書きました。
そのメッセージを読んだ時、わずか1ヶ月前に自分が書いた短い文なのに、あきらめずにできた自分を褒めてくれた嬉しさで涙が止まらなくなりました。
その日から、やるべきことがクリアに見えるようになりました。
心理的効果
このワークは、心理学でいうセルフ・コンパッション(自己への思いやり)とメタ認知を同時に鍛えます。
自分を俯瞰することで、ネガティブな思考ループを抜けやすくなり、未来に向けた行動意欲が高まります。
「他者の幸せ」を含めた未来ビジョンの描き方
自分だけの未来は、すぐに限界がくる
未来を思い描くとき、多くの人は「自分の成功」や「自分の理想の生活」から始めます。
もちろんそれも大切ですが、それだけだと、達成した瞬間にモチベーションが薄れたり、虚しさがやってくることがあります。
本当に心が満たされる未来ビジョンは、自分の幸せの中に他者の幸せも自然に含まれているものです。
他者を含める3つの理由
- 持続力が高まる
他者の喜びや成長がモチベーションの一部になるため、挫折しにくくなる。 - 共感と応援を得られる
あなたのビジョンに他者が共鳴し、サポートしてくれる仲間が増える。 - 自己肯定感が自然に上がる
誰かの役に立つことで、「存在価値」を実感できる。
描き方のステップ
- 自分の理想の未来を書く
収入、住まい、健康、人間関係など、自分が満たされている姿を自由に描く。 - そこに関わる人を思い浮かべる
家族、友人、仲間、見知らぬ人でもOK。 - その人たちがどう幸せになっているかを加える
例:自分が健康でいることで、家族が安心して笑っている。
自分の活動が、誰かの自信や希望になっている。
未来ビジョンの文章例
わたしは近隣住人とのトラブルが絶えない喧騒の町から引っ越し、現在は心地よい海辺の町に暮らしています。
仕事は自分のペースで進められ、月に数日はカウンセリング活動をしています。
その活動を通じて、自分を責めていたクライアントが自尊心を抱くようになって笑顔を取り戻し、家族とも良い関係を築いています。
わたしの周りには、互いに尊重し合い、助け合える仲間たちがいて、いつも温かい空気が流れています。
わたしはその智慧を深めるために、毎日本や動画、セミナーなどに出席して学びを深めて経験を積んでいます。
ワークの効果
こうして他者の幸せを含めた未来を描くと、自分の行動が誰かのためにもなる感覚が芽生えます。
これは心理学でいう「自己超越的目標」にあたり、幸福感や人生の満足度を長期的に高める効果があります。
日常でエネルギーの流れを整える小さな習慣
性もお金も心も、すべては「エネルギー」です。
それは川の水のように、流れているときは澄み、滞ると濁っていきます。
だからこそ、日々の生活の中で、エネルギーが健やかに循環する状態を保つことが大切です。
1. 感情をこまめに観察する
- 嫌な出来事のあと、「今、私は何を感じている?」と一言メモ
- 喜びや感謝も書き留めておく
感情を意識することで、抑圧や滞りに気づきやすくなります。
2. お金の出入りを「感謝」でチェック
- 支払いのとき「このお金が誰かの役に立ちますように」と心で唱える
- 収入のときは「受け取らせてもらえてありがとう」と意識する
感謝の習慣は、お金への恐れや罪悪感を和らげ、流れをスムーズにします。
3. 体を使って性エネルギーを循環させる
- 軽いストレッチやダンスで骨盤まわりを動かす
- 呼吸法で下腹部に意識を向ける
性エネルギーは、身体感覚を通して解放・活性化しやすくなります。
4. 小さな「布施」を日常に入れる
- コンビニで募金する
- 困っている人に声をかける
- 知識や時間を惜しまず分ける
布施の行動は、エネルギーの循環を外へ広げ、あなた自身の心の潤いにもつながります。
5. 一日の終わりに「流れの振り返り」
寝る前に、「今日はどんなエネルギーを受け取り、どんなエネルギーを渡したか」を思い返してみましょう。
これだけで、無意識のうちにエネルギーを整える習慣がつきます。
こうした小さな積み重ねは、性やお金といったテーマだけでなく、人生全体の流れを軽やかにします。
過去を癒し、未来を創るエネルギーの土台は、日常の中にこそあるのです。
まとめ──過去も未来も、あなたの今から変わる
過去は癒せる、未来は創れる
出来事は変えられませんが、その意味づけは変えられます。
未来は白紙であり、今の選択がそのページを彩ります。
魂の成長は「否定しないこと」から始まる
性もお金もエネルギーとして肯定し、正しく扱うこと。
それが過去を癒し、未来を創る力になります。
あなたの魂は
──言葉にならない感覚で、いつも深く語りかけています。
その声に、静かに耳を澄ませてみませんか?
エネルギー調整セラピスト
かんまに